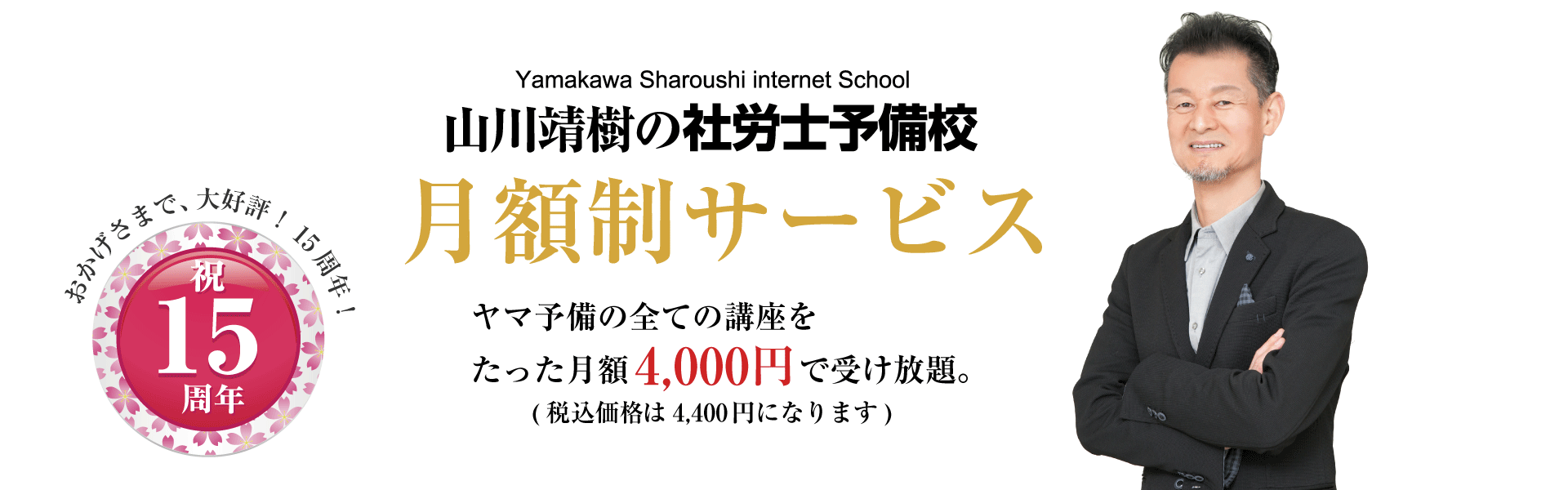ニックネーム | *** 未ログイン ***
国民年金法/年金の改定率
anya910 2025-04-19 17:51:25
改定率の算出方法について、令和7年の数字を使用して、具体的に教えていただきたいです。
改定率=名目手取り賃金率×調整率×前年度の改定率
調整率=公的年金被保険者総数の変動率×0.997
名目手取り賃金率=物価変動率×実質賃金変動率×可処分所得割合変化率
なのですよね?
厚生労働省の資料には下記の通り記載してあり、理解が及びませんでした。
名目手取り賃金変動率(2.3%)=物価変動率(2.7%)+実質賃金変動率(▲0.4%)+可処分所得割合変化率(0%)
マクロスライドによる調整率(▲0.4%)=公的年金被保険者総数の変動率(▲0.1%)+平均余命の伸び率(▲0.3%)
2.3%-0.4%=1.9%引き上げ
なぜ乗じないのでしょうか。また、前年度改定率はどこで使われるのでしょう。
どうぞよろしくお願いいたします
お尋ねになっている「厚生労働省の資料」に使われている用語は、必ずしも法令通りではありません。
例えば、資料で使われている「改定率」は法令用語としての「改定率」ではないようで、単に前年から比較して変わった程度を表す、説明のための用語のようです。
また、可処分所得割合変化率も0なのですから、どう書いても結果に影響しません。
他にも同じような部分があるかもしれません。
受験用の教材が、受験に特化して編集され、必ずしも法令通りではなく、それは短所ではなくて、受験という目的に対して長所であるのと同様に、こういった「いいかげんさ」は、「国民への広報」という目的に照らした場合には合理的です。
受験対策ならば、法令の内容を分かりやすく、しかしケースに応じて正しく伝える必要がありますが、国民への広報なら、法令に照らした用語を使い、細かい内容を書いても、一般的な国民にとっては理解が難しく、煩雑なだけです。
一般的な国民への広報なら、なぜ年金が改定されるのか、そしてその改定結果がさらに再調整されるのがなぜか、それらの結果がどうか、が、分かりやすく伝わるのが大切です。
厚労省資料の「年金額改定についてお知らせします」の資料には、最後の2ページにとても分かりやすい図表が載っていて、国が国民に伝えたいのは、この図表の内容なのです。
法令の正しい内容を、正しい用語を使って伝えたいのではありません。
このため、お尋ねのような比較には答えることができません。どうしてもであれば、資料を作成された然るべき機関に問い合わせてみてください。
また、これは過去問をされたらわかることですが、例えば前年度改定率についての問題は、この20年くらいの間、保険料の改定でしか出たことがありません。
調整率という用語を使った出題もありません。
しかし、国民年金法で改定率についての出題がないのかというと定期的にあります。最近であれば、R2問6A、R3問8D、R5問8Aなどです。
内容を見て分かるように、あなたが気にしておられるような細かい内容の問題は出ていません。
このため、各社の受験テキストでも、年金額の改定についての重要度は比較的低くなっているはずです。
出題が定期的にあるのに重要度が低いのは、内容の複雑さに対して出題がそれほど難しくないからです。
受験対策としては、重要ポイントだけ押さえて軽く流す部分です。
しかし実感としてそれを知るには、過去問とテキストを往復するトレーニングが必要です。
年金額の改定制度は条件に応じて複雑で、受験用テキストはその内容をひととおり書かない訳にはいきません。
受験される方はそれを読み理解する必要はあるのですが、全てを理解する必要はありません。
最初は口述講義に沿って読み、その範囲で理解すれば十分です。
そして受験勉強中に疑問が生じたら、これは年金額の改定だけではありませんが、付箋でも貼って先に進むことをお勧めします。
受験勉強中に疑問が生じたら、テキストを広い範囲で読み返し、口述講義を聴き直すことは必須です。
しかしそれでも疑問が解決しなければ、付箋でも貼って先に進むことをお勧めします。
受験対策は、テキストと口述講義、そして過去問を使った反復トレーニングです。
テキストと過去問を学習レベルに応じて工夫しながら何度も往復するトレーニングを積んでいかれれば、本試験の出題がどういった内容なのかが見えてきて、テキストの読み方が変わります。
そして、生じていた疑問も、その多くは「ああ、あれはそういうことだったのか」となって解決したり、「疑問に思っていたけど受験に関係ないね」のような気づきがあって、受験対策上の疑問としては消滅します。
特に「「疑問に思っていたけど受験に関係ないね」のような気づき」は大切です。そのような気づきが、不要な迷いを削ぎ落とし、受験に必要な知識とその使い方を整理してくれます。
「わからない」→「知らなきゃ」ではなく、受験対策とは、本試験の内容に沿ってテキストの知識を整理し、受験の場で実戦的に使えるように鍛えるトレーニングです。
トレーニング中にご自身が気づいて得たものは強いので、学習中の疑問の解決は、そのようなトレーニングの中でされることをお勧めします。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2025-04-20 12:22:48