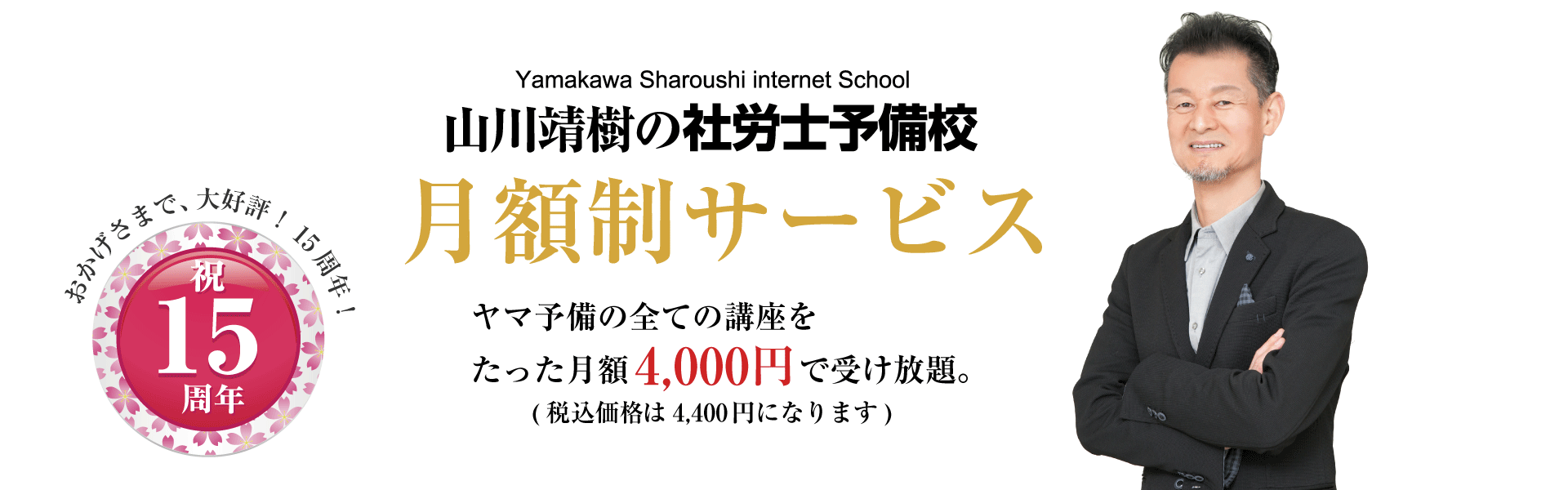ニックネーム | *** 未ログイン ***
国民年金法/平成25年国民年金問9の肢Aについて
aoyama1122 2025-06-30 22:50:39
平成25年国民年金問9の肢Aの問題文:
【ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した場合の死亡に関する給付等について。なお、男性は障害基礎年金の受給権を取得したことがない】
男性が死亡した当時、生計を維持していた者が同居していた80歳の母(老齢基礎年金のみ受給中)だけである場合、母は遺族として、死亡一時金と遺族厚生年金の受給権を取得し、すべて受給することができる。
について、男性が死亡したときは厚生年金被保険者でなかったので遺族厚生年金の受給権は発生しないと思ったのですが、この問いの答えは「正解」です。なぜ遺族厚生年金の受給権が発生する、の解答が正解なのでしょうか?
受験対策上、疑問が起きたときに、ご自身の頭の中の知識に頼られるのは、厳しい言い方をすると論外です。
学習中の疑問は、ご自身の知識の誤りや不足を教えてくれていることが多いのです。
まず、ご自身の頭の中の知識で判断した上で、解らなければテキストを幅広く読み返し、口述講義を聴き直す習慣を付けてください。
遺族厚生年金において「誰が死亡した場合に支給されるのか?」を書いているのは法58条1項です。
これをテキストで学習し直してください。
「被保険者が死亡したとき」以外に、3つも要件がありますよ。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2025-07-01 09:13:32
poo_zzzzz 様
ご回答いただき、ありがとうございました。
早速テキストにて「「被保険者が死亡したとき」以外」の要件を確認したところ、その中に、「老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上である者に限る)又は保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上である者(長期要件)」とありました。
本問題の、「54歳で亡くなった男性」は、国民年金と厚生年金の被保険者期間を有する者で、「保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上である者」に該当すると判断いたしました。
ですので、本問題文:
「男性が死亡した当時、生計を維持していた者が同居していた80歳の母(老齢基礎年金のみ受給中)だけである場合、母は遺族として、死亡一時金と遺族厚生年金の受給権を取得し、すべて受給することができる。」は正解である、と理解いたしました。
「厚生年金の被保険者でない者だから、遺族厚生年金支給要件に該当しない」ということにばかり気が取られておりました。
気を付けます。ありがとうございました。
aoyama1122 2025-07-01 16:40:47
そもそも「厚生年金の被保険者でない者だから、遺族厚生年金支給要件に該当しない」なんてことは、テキストのどこにも書いていないでしょう?
これは、あなたが勝手に作り出した誤った知識です。
そして、受験学習は、こういった、ご自身の中の、誤った知識や知識不足との戦いです。
あなたがこのように覚えておられたことは悪いことではなく、ごく自然なことです。
ただ、その結果生じた疑問の解決を、自助努力もせず他人に求められたことはよくありません。
まず疑うべきは、あなたの頭の中の知識であり、ご自身の学習方法なのです。
疑問が生じたときは、単に正しい知識を得ようとするだけではなく、ご自身の学習方法を正すチャンスなのですから、まずご自身で学習の見直しをされるべきです。
「気をつけるべきこと」は、間違ったことそのものではなく、正しい学習の手順だと思います。
疑問を感じたら、ご自身の頭の中で判断せず、必ずテキストに戻り、必要であれば用語の定義に遡るつもりで読み込み、口述講義を聴くようにしてください。
そしてそれで分からなかったら付箋でも貼って先に進んで大丈夫です。
テキストと口述講義、そして過去問を正しく使い、工夫して繰り返してトレーニングする内に、受験にとって解決が必要な疑問はほとんど解決するはずです。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2025-07-02 17:02:16