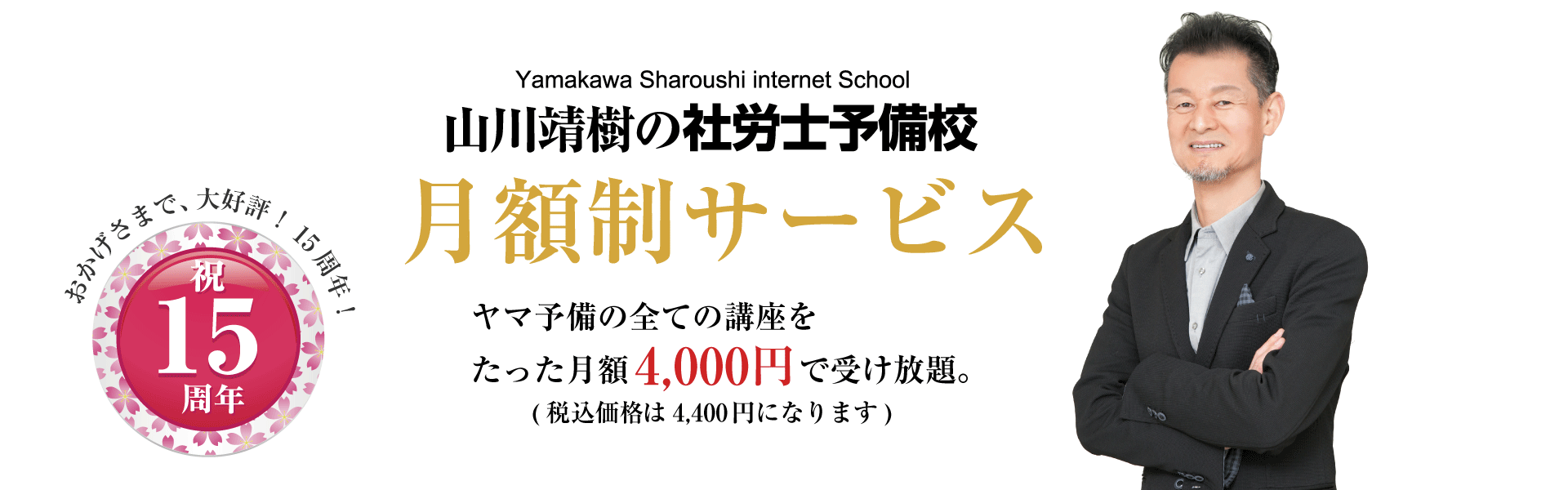ニックネーム | *** 未ログイン ***
健康保険/強制適用事業の常時5人の考え方
YU010 2025-07-16 21:37:47
適用業種に該当する個人経営の事業所で常時5人以上の従業員を使用する場合強制適用事業所となるの「常時5人」の考え方について健康保険法と厚生年金保険法で同じ考え方で良いのか、疑問に思って答えが見つかりません。
健康保険法のテキストp29には、常時5人については適用除外に該当する人も数えるとありますが、
厚生年金保険法のテキストではその記載が見つかりません。
調べていると士業が法定業種に追加された際の日本年金機構の情報では、常時5人については通常の労働者の3/4以上ある人をいうとありました。
健康保険法と厚生年金保険法で、強制適用事業所の要件の常時5人以上の数え方は違うのでしょうか。
違う場合、健康保険と厚生年金の強制加入になるタイミングがズレることもあるという事なんでしょうか。
この質問広場の新規投稿画面の冒頭に、赤字で、「※教材についてのご相談やご質問、教材の配送状況のお問合せなどは、「質問広場」への投稿ではなく、直接事務局にメールにてご連絡いただきますよう、お願いいたします。」とあります。
注意事項にも、同様の記述が、赤字で書かれています。
今回書かれている内容は、やまよびさんが出しておられる教材に書かれている内容ついてのご質問のようですので、この注意書きに従われるべきだと思います。
また、質問広場の注意事項には、間接的にですが、質問広場は、やまよびさんのスタッフの方が回答する場では無いことを示唆する記述があります。
新規投稿画面に、やまよびの事務局さんへのメールのリンクが張られていますので、そちらを利用されることをお勧めします。
ただ、この部分はややこしいので、教材を離れた一般論として書いておきます。
健康保険・厚生年金保険の両保険の適用事業所であれば、年齢の制限に引っかかる場合を除き、健康保険と厚生年金保険の被保険者資格は同時に取得します。
「常時5人以上」については、昭和18年4月5日保発905号通達に、「被保険者となることができない者であっても当該事業所に常時使用される者についてはこれを算入すべきものとする」があります。
保発通達ですが、厚生年金保険法でも引用されます。おそらくですが、お手持ちのテキストにもこれが書かれていると思います。
これについては昭和55年6月6日に当時の厚生省で内かん(省庁の内部連絡)が発出され、「常時5人以上の従業員」を算定するにあたっては、「常用的使用関係」に該当する者は算入し、「常用的使用関係」に該当しない者については算入しないと解されることが明示されています。改正前の厚生年金保険法の疑義照会でもこれが引用されています。
問題は「常用的使用関係」にあり、改正後は4分の3基準が明示されたため、日本年金機構の情報ではこれを基準として書かれているものと思われます。
つまり、もし、お手持ちのテキストの記述が「被保険者となることができない者であっても当該事業所に常時使用される者についてはこれを算入すべきものとする」のような内容であるなら、そのテキストの記述と、日本年金機構の情報は矛盾していません。
なお、適用除外に該当するが常時使用関係にある者(5人に数える者)は、健康保険ならば船員保険の適用がある者、国民健康保険の適用がある者、後期高齢者医療の適用がある者などを指し、厚生年金保険であれば70歳以上の者を指します。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2025-07-17 12:19:09
ご回答ありがとうございます。
テキストの話をしてしまい失礼しました。
「常時5人以上」を考える際に4分の3基準を満たさなような働き方をするパート・アルバイトの人を含んで5人という解釈をずっとしていたのですが、どうしても「常用的使用関係」で4分の3以上の基準で混乱しています。
私の最初の解釈が間違っているのでしょうか。
例えば、5人の従業員を雇う個人事業主(適用業種)で、5人のうち4人がフルタイム勤務者、1人が週20時間のような働き方をする場合は強制適用事業にならないということでしょうか。
YU010 2025-07-17 19:17:00
> テキストの話をしてしまい失礼しました。
テキストの話をするのが失礼なのではありません。
ヤマヨビさんは、教材についての質問は「質問広場ではなく」「事務局にする」ように書かれています。
これを守るべきであると申し上げています。
また、教材は必ず編集を経ますから、教材が絡む質問は、誰が編集された教材であっても、教材を編集された方に直接聞くべきだと思います。
先にも書きましたが、「常時5人以上」の数え方については、昭和18年4月5日保発905号通達に、「被保険者となることができない者であっても当該事業所に常時使用される者についてはこれを算入すべきものとする」があります。
これは、令和5年の健保問1Aの問題に、ほぼそのまま出題されています。
おそらくですが、あなたの健康保険のテキストに載っているのも、これと同趣旨であると思います。
(1) 被保険者となることができない者であっても
(2) 当該事業所に常時使用される者については
(3) これを算入すべきものとする
質問された方は、この通達の(1)の部分にだけ目を奪われておられますが、この通達において(1)はいわばおまけで、重要なのは(2)です。
この通達の本質は(2)(3)の「当該事業所に常時使用される者についてはこれを算入すべきものとする」です。
しかしこの書き方だと「適用除外の従業員はどうなるのですか?」という疑義があるので、(1)が書き加えられているのです。
つまり、この通達が言いたいことは、被保険者になるべき者であっても、被保険者となることができない者であっても、「常時使用される者」を、常時5人を数える場合に算入するということです。
逆に言えば、被保険者となることができない者であっても、「常時使用される者」に該当しなければ、常時5人を数える場合に算入しません。
例として、令和4年10月に士業に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が行われ、一定の士業について、常時5人以上であれば個人事業でも健康保険・厚生年金保険共に強制適用になったときの厚生労働省の広報資料を見てみましょう。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/20211118.html
このURLの2.の(1)に「常時5人以上の従業員を雇用している士業の個人事業所」とあり、そのすぐ下に「※従業員とは正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず、1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上ある人をいいます。」とあります。
このことから、厚生労働省が健康保険法・厚生年金保険法において考えている「常時使用される者」がどのようなものかは明らかであると思います。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2025-07-19 10:53:09