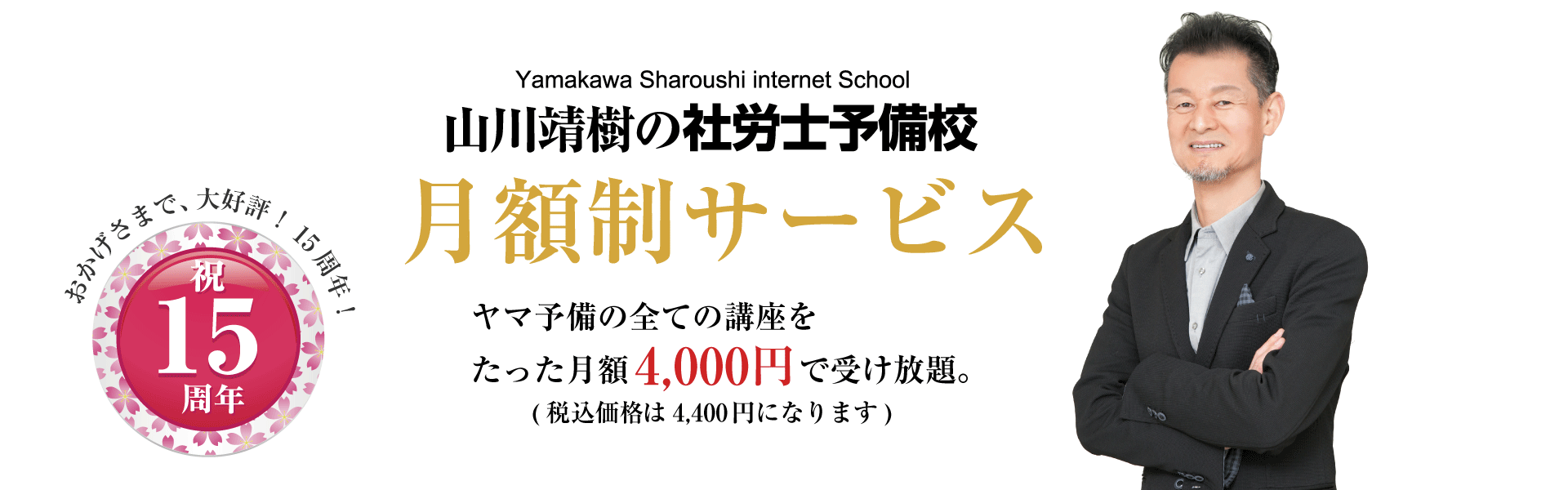ニックネーム | *** 未ログイン ***
厚生年金保険法/在職老齢年金制度の繰下げ加算について
anya910 2024-12-28 23:01:21
混乱してしまった内容について、質問させて下さい。
65歳以後も被保険者であり、在職老齢年金による調整の対象となる者は、支給停止される額を除いた残余の額のみが繰下げの対象になります。つまり、全額支給停止になる者は、繰下げの対象になる年金がないということになると思います。しかし、在職老齢年金制度で、繰下げ加算は調整の対象外であり、年金額が全額支給停止となる場合でも支給されるというのは、どういうことなのでしょうか。繰下げ加算額のみ支給されるということはないと思うのですが、私は、どこかで勘違いをしているのでしょうか。
申し訳ないですが、何をご説明申し上げたら良いのかよく分かりません。
>支給停止される額を除いた残余の額のみが繰下げの対象になる
① これは、老齢厚生年金の受給権発生(原則65歳)から、繰下げの申し出により老齢厚生年金が支給されるまでの期間の長さに応じて発生する加算額の計算の元になる老齢厚生年金の話ですね?
>在職老齢年金制度で、繰下げ加算は調整の対象外であり、年金額が全額支給停止となる場合でも支給される
② これは、繰下げの申出後に支給される老齢厚生年金が、その時点での在職調整で支給停止の対象となる場合の話ですね?
この①②を比較して、「①なのに②はどういうことなのでしょうか」とおっしゃっているようですが、上記の①は受給権発生から繰下げの申出前の期間であり。②は繰下げの申出による年金支給開始後の期間です。
本来は比較対象になるはずのない「完全に異なる期間」である①②を比較して、質問された方が疑問をもたれた理由が分からないのです。
>繰下げ加算額のみ支給されるということはないと思うのですが
繰下げとは関係なく、例えば経過的加算は在職調整の対象になりません。
これは、経過的加算が、本来は基礎年金から支給されるべき額や旧法制度からの経過的な額であり、法42条の老齢厚生年金とは性質が異なるからです。
このため在職調整により老齢厚生年金が全額支給停止でも、経過的加算による額は支給されます。
あなたのお考えだと、これも「支給されるということはないと思う」のでしょうか?
逆に加給年金額は、在職調整により老齢厚生年金が全額停止だと支給停止の対象になります。私は加給年金額の趣旨から考えてこちらを少し奇異に感じますが、ここは制度が何を見ているのか?の問題であり、それを覚えるのが受験勉強です。
最後に、これはご存じだと思いますが繰下げについて念のために書いておきます。
まず、繰下げと繰下げ申出までの在職調整の関係のイメージは下記URLをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-02.html#cms01
国民年金と厚生年金の給付の目的は「社会の防貧」です。
老齢や障害や被扶養利益の喪失によって貧困に陥る世帯が発生することを抑止し、そういった世帯が増えることにより社会が貧困化するのを防ぐのが目的です。
そしてこれらは「社会保険」であり、受益予定者からあらかじめ保険料を徴収するという自助の制度であると共に、現役世代が受給世代を支える世代間扶養による共同連帯の制度でもあります。
目的が社会の防貧であり、費用の負担が共同連帯であることを考えると、高齢になっても十分な収入があるなら、年金の支給はしないでもいいのでは?という考えもあります。
しかし、本人の保険料の支払いがあることに加え、高齢者の勤労意欲を削がないためにも、年金給付を一律でなくすのではなく、段階的に支給停止し、また、一部の年金については支給停止の対象にしないことにしました。
これが現在の在職年金制度です。
老齢厚生年金の受給権は被保険者期間と年齢(原則65歳)により、請求を待たず、自動的に発生します。
受給権は自動で発生しますから、例えば68歳で老齢厚生年金を請求した場合、受給権が発生した月(原則65歳に達した月)の翌月から請求した68歳までの年金は、遡って一括で支給されるのが原則です。
この場合の請求が66歳以後(原則)であれば、そのときに老齢厚生年金の請求時に繰下げの「申出」をすることができます。
この「申出」は、平たく言うと「今まで我慢した年金は要らないから、その権利を失う年金の期間に応じて、今後支給される年金を増額してください」という申出です。
この場合、老齢厚生年金の支給開始は、受給権が発生した月の翌月ではなく、繰下げの申出をした月の翌月からになり、そこまでの年金は受け取ることができなくなります。
つまり、繰下げは「支給開始時期」についてのオプションであり、繰下げの申出をした場合は、そこまでに支給されるべきであった年金は支給されず、その権利を失った期間に応じて、その後の年金を増額する制度です。
この場合、老齢厚生年金の受給権発生から繰下げ申出までの、いわば「我慢している期間」に、在職年金制度により老齢厚生年金が満額支給されない月があったら、その月について本来の規定通り0.7%で増額するのは制度の趣旨に合わないでしょう?
仮に繰下げの申出をせずに遡って老齢厚生年金を受給した場合でも、その月の年金は満額支給されないのですから、その分は繰下げ加算から除くのは当然でしょう?
仮に全額停止であった月があるなら、その月は繰り下げても「何も我慢していない」のですから、繰下げ加算の計算対象にならないのも当然ではないでしょうか?
このため、老齢厚生年金の受給権発生から繰下げ申出までの期間に在職老齢年金により老齢厚生年金が満額支給されなかった場合は、月単位の支給率を元にした平均支給率を求め、繰下げ加算の率をコントロールします。
そして繰下げによる老齢厚生年金が支給されるようになったあと、在職調整により老齢厚生年金を支給停止する場合、繰下げ加算率によって増額された額は、「過去の年金を我慢した、いわばご褒美」ですから、その時点での在職調整による支給停止の計算の対象にしないのも、また当然だと思いますが、いかがですか?
参考になった:2人
poo_zzzzz 2024-12-30 22:53:29
丁寧なご説明、ありがとうございました。現時点で在職調整で全額支給停止になっていても、過去の繰下げ加算で増額された額は、支給されるという理解でよろしかったでしょうか。
anya910 2024-12-31 22:08:46
>現時点で在職調整で全額支給停止になっていても、過去の繰下げ加算で増額された額は、支給されるという理解でよろしかったでしょうか。
これは、あなたがお持ちのテキストに書いてあるのではないですか?
① 在職調整で老齢厚生年金が全額支給停止であっても、老齢基礎年金、経過的加算及び繰下げ加算額は支給される。
② 加給年金額は在職調整があっても全額支給されるが、在職調整で老齢厚生年金が全額支給停止になると加給年金額も支給停止になる。
この①②は、表現の違いはあっても、どの受験対策校のテキストでも必ず書いてあるはずです。
疑問が生じたときに頼るべきは、あなたの頭の中の知識や常識ではありません。
受験学習中に疑問が生じたときは、それまで目に見えなかったあなたが持っていた「壁」が見える姿になって現れたときです。
ご自身の知識を正す絶好のチャンスです。
このチャンスを、ご自身の知識や常識にとらわれてみすみす逃がしたり、他人に頼って結果だけ知るのは、受験対策として良い方法とは思いません。
必要なのは、知識そのものではなく、知識を得る方法とそのプロセスを知ることです。
疑問が生じたら、とりあえず頭の中の知識は捨て、疑問のか所だけでは無く、できるだけ広い範囲でテキストを読み直し、口述講義を聴く習慣を付けてください。
そしてそれで疑問が解決しなかったら、付箋でも貼ってその疑問を先送りしてください。
受験学習は一方通行ではなく、テキストと口述講義そして過去問を用いて反復するトレーニングです。
反復する段階に応じて正しくテキストと過去問を使えるようになれば、学習初期の疑問のほとんどは解決するか、受験対策上の必要性を感じなくなると思います。
例えば、今回のコメントのあなたの問いかけは、本試験過去問のH26択一厚年問6CやR06択一厚年問9Eに、ほぼそのままの形で出題されています。
今年学習を始められた方なら過去問にはまだ手が出ていないと思いますが、過去問を解き始めれば答えはそこにあります。
まぁ、その前にテキストにも書いてあるはずですが。
そうなるのがなぜ?ということであれば、前回の私のコメントをもう一度ご覧ください。
答えが知りたいだけであるなら、それはテキストにも、過去問にもあります。他人に確認することではありません。
もう一度書きますが、受験学習(特に初期)に必要なのは、知識そのものではなく、知識を得る方法とそのプロセスを知ることです。
追記
質問された方の文章を見ていると、なんとなくですが、老齢厚生年金の受給権発生、繰下げの申出、老齢厚生年金受給開始後の期間、の時系列と、厚生年金保険の被保険者期間(及び70歳以降の在職調整期間)の関係が、うまく整理できていないように感じます。今一度丁寧に整理されることをお勧めします。
もし違っていたら失礼をお詫びしますが、脆弱な基礎の上に知識を並べても受験の役には立たないので・・・
参考になった:2人
poo_zzzzz 2025-01-01 11:57:53