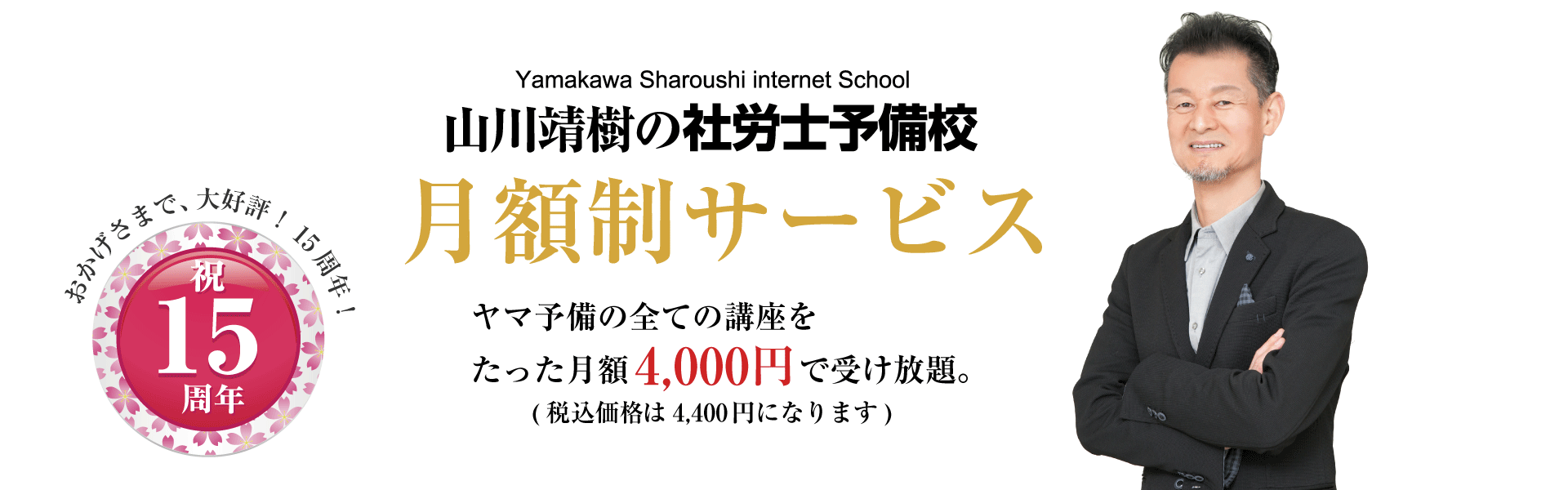ニックネーム | *** 未ログイン ***
雇用保険法/失業等給付 被保険者期間の算定について
Benimaru 2025-04-18 13:13:18
某予備校のテキストを利用して独学をしている者です。
雇用保険法の失業等給付において、被保険者期間の算定(計算)の仕方がよくわからないのでご教授いただけますと幸いです。
pp.322~323
「①被保険者として雇用された期間を、資格喪失日の前日からさかのぼって1箇月毎に区切っていき、このように区切られた1箇月の期間に賃金の支払の基礎となった日数(以下「賃金支払基礎日数」という)が11日以上ある場合に、その1箇月の期間を被保険者期間の1箇月として計算する。 ②このように区切ることにより1箇月未満の期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が11日以上あるときに、その期間を被保険者期間の2分の1箇月として計算する。」
という説明です。
例が2つに図表の解説が載っておりますが、いまいち理解が出来ず困っております。
特に②からの部分が混乱を招くので、教えていただけましたら幸いです。
何卒宜しくお願い申し上げます。
これは、お使いになっている教材を編集された方にお尋ねになるのが良いと思います。
受験教材は、その目的のため法令をデフォルメし、順番を入れ替えたりして、受験対策に特化した編集をします。
そこには編集された方の意図があるのですから、説明は編集された方から受けるのが良いと思います。
また、質問された方が切り出された箇所以外への参照もあるので、切り出された部分だけで、第三者が論じるべきものではないと思うのです。
また、受験対策中に起きた疑問は、すぐに解決する必要はありません。
解決しなくても、付箋でも貼って先に進み、テキストと過去問を学習レベルに応じて工夫しながら何度も往復するトレーニングを積んでいかれれば、「ああ、あれはそういうことだったのか」とか「疑問に思っていたけど受験に関係ないね」のような気づきがあり、疑問のほとんどは解決するか、受験対策上の疑問としては消滅します。
トレーニング中にご自身が気づいて得た知識は強いので、学習中の疑問の解決は、そのようなトレーニングの中でされた方が良いと思います。
ヒントだけ書くと、
(1)雇用保険法において「被保険者期間」は、法14条に定められた特別な意味を持つ用語であり、「被保険者であった期間」(質問された方の教材では「被保険者として雇用された期間」)とは意味が異なる。このため、「被保険者であった期間」であっても「被保険者期間」にならない場合があること。
(2)「被保険者期間」は、それが一定の期間に、一定の数あると、基本手当を受ける権利が生じる、そのような期間であること。
(3)「被保険者期間」は、資格喪失日の前日から遡る1か月ごとの期間について算定すること。このため、原則として、例えばある月の10日から前月11日のような完全な1月について「1か月」の「被保険者期間」が算定される。例えばある月の10日から前月の11日まで遡ろうとしたが、被保険者資格取得日が前月15日であったためそこまでしか遡れなかった場合のような不完全な月については、その不完全な月の日数が15日以上あり、この期間に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合は、それを「2分の1月」の「被保険者期間」として算定する。お書きになっている②はこの不完全な月のことだと思います。
参考になった:0人
poo_zzzzz 2025-04-19 10:34:46
poo_zzzzz様
ご返信いただきありがとうございます。
受験対策に必要な心得までご指導いただき、誠にありがとうございます!
ヒントのご説明も大変わかりやすく感じました。
トレーニングでの疑問解決に向けて学習に励みたいと思います。
ありがとうございました!
Benimaru 2025-04-19 18:45:39
そうですね、頑張ってください。
ところで口述講義は聴いておられますか?
どのような教材を使っておられるのか分かりませんが、受験用教材の多くには口述講義が付いていて、教材はそれを聴くことを前提に編集されています。
もし聴いておられないなら、口述講義を聴きながら学習を進めることをお勧めします。
参考になった:0人
poo_zzzzz 2025-04-20 10:39:24
ありがとうございます。
口述講義に関しては、教材元の講義は受けておりません。
重要性については把握しておりますが、経済的な理由から今現在は通学は見送っております。
Youtubeで自分で調べて動画を観たりすることで知識を補うかたちで進めております!
Benimaru 2025-05-11 11:38:53
経済的な事情はやむを得ない部分はあると思います。
しかし、今回あなたは「被保険者であった期間」と「被保険者期間」の違いをテキストの範囲で理解されていなかったように思います。
そしてこのような、差がなさそうであること、違いそうで同じであることの説明は、出版物であるテキストではなかなかできません。
このため、多くの受験用テキストは、特定の講師の口述講義を聴くことを前提に編集されていて、口述講義はCDやDVDでテキストに付いているか、出版元の受験対策校がインターネットで提供している(有料視聴の場合あり)のが一般的で、通学や通信は必須ではありません。
あなたが有り余る時間を持っておられるならば別ですが、受験対策において最もコストパフォーマンスが悪いのは再受験であると思うので、ここは押して口述講義の視聴をおすすめします。
あなたがご自身の都合で口述講義を聴かないのは自由ですが、わたしはそれを、受験対策において最低限ご自身でされるべき自助努力の一部だと考えています。
他人の時間と知識と労力を頼る前に、ご自身の受験対策としてされるべきことがあるように思います。
参考になった:0人
poo_zzzzz 2025-05-12 16:08:46