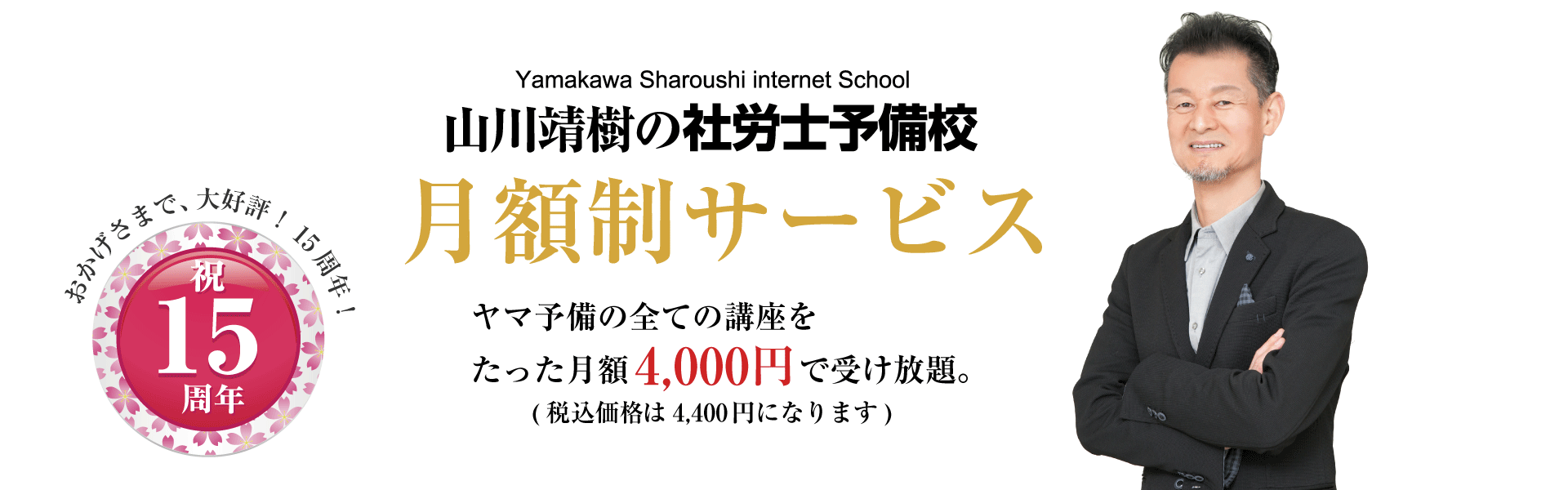ニックネーム | *** 未ログイン ***
国民年金法/合算対象期間と受給権の発生
cappuccino 2025-04-27 18:17:18
受給資格期間が25年必要だったときの問題なのですが、
「昭和36年4月~65歳に達するまでの間、合算対象期間が288月あるのみで受給権を満たしていなかった者が、65歳以降に後納保険料12月を納付した。」
場合、老齢基礎年金の受給権が発生しないとのこと。なぜでしょうか?(間違い?発生する?)
これは過去問ではなさそうですね。
後納保険料制度が存在した平成24年以降の本試験問題で「後納保険料」という用語を使用した本試験問題は無いはずです。
本試験ではない作問のようですので、この問題を作問された方にお尋ねになるのが良いと思います。
教材は、その目的のため編集します。
また、質問された方が切り出された箇所以外への参照の可能性もあるので、切り出された部分だけで、第三者が論じるべきものではないと思います。
編集された方の意図があるのですから、説明は編集された方から受けることをお勧めします。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2025-04-27 21:46:46
早速の御返答ありがとうございます。
GW中だったため、返信が遅れて申し訳ありませんでした。
御指摘のとおり、これは過去問ではありません。アドバイスいただいた通り、作問者に尋ねましたところ、
まず、「昭和36年4月~65歳に達するまでの間、合算対象期間が288月あるのみで受給権を満たしていなかった者」は
法26条から、「保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生等の保険料の納付特例及び保険料納付猶予制度の
規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く)を有する者が65歳に達した」時点で合算対象
期間288月のみしかないので受給権は発生しません。それに、65歳到達後に後納保険料(既に制度はありませんが)を
12月納めたとしても、後納保険料は納めた時点から将来にむかってのみ(つまり65歳以降に納めたことになる)
保険料納付済の効力を発生させるため受給権は発生しない、なお、実務上このような事例で(受給権が発生しないのに)
後納保険料を納めさせることはあったのか?と尋ねたところ、「実務上は後納保険料を納めても受給権は発生しない」
旨の説明をするとのことでした。
ありがとうございました。
cappuccino 2025-05-07 19:08:41
解決して良かったです。
私の知る限り、年金法でここを突っ込んだ設問は初めて見ました。
おっしゃるように後納保険料制度は平成の時代に終わっているので、受験対策としては重要ではありません。
また、後納保険料の納付については厚生労働大臣の承認が必要だったので、お尋ねの場合納付はできなかったと思います。
後納保険料については措くとして、今現在の受験対策として国民年金法26条を簡単に説明します。
国民年金法26条
老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(略)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。
老齢基礎年金は、①保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する②いわゆる受給資格期間を満たすことを前提に「65歳に達したとき」に支給されます。
「65歳に達したとき」ですから、65歳到達時に、①②を満たしていないと、その後に①②を満たしても、国民年金法26条を満たせず老齢基礎年金の受給権が発生しません。
しかし、65歳以降に任意加入して受給資格期間を満たし、老齢基礎年金を受給することはできます。
これは、法26条にかかわらず、60法附則18条に特例があるからです。
60法附則18条
65歳に達した日において、保険料納付済期間(略)又は保険料免除期間(略)を有する者であって次の各号のいずれにも該当しなかったものが、同日以後の国民年金の被保険者期間を有するに至ったことにより次の各号のいずれかに該当することとなったときは、同法第26条に定める老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢基礎年金を支給する。
「次の各号」は省略しますが、簡単に言うといわゆる受給資格期間(又はその特例、以下単に受給資格期間という)を満たしている場合が該当します。
つまり、この60法附則18条の特例は、65歳において受給資格期間を満たすことができず、老齢基礎年金の受給権を持たなかった者が、65歳後に受給資格期間を満たした場合に適用されます。
これにより、65歳後に任意加入で受給資格期間を満たした場合は、この60法附則18条により法26条に該当したものとみなされて老齢基礎年金の受給権を得ます。
しかし、この60法附則18条をよく見てください。
・65歳に達した日において保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者
・65歳に達した日以後の国民年金の被保険者期間を有するに至ったこと
を両方満たしていないと、60法附則18条の特例にも該当しないのです。
これに対し厚生年金保険法の老齢厚生年金では、
厚生年金保険法42条
老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至ったときに、その者に支給する。
一 65歳以上であること。
二 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。
このように、老齢厚生年金は、③被保険者期間を有すること④65歳以上であること⑤いわゆる受給資格期間を満たすことの3点をすべて満たせば、それらをすべて満たした時期に関係なく受給権が発生します。
今現在の受験対策としてこの部分を整理するなら、上記のようになると思います。
まぁ、ここまで考えなくても受験には差し支えないと思いますが・・・
参考になった:2人
poo_zzzzz 2025-05-07 22:40:53
追記です。
> 後納保険料は納めた時点から将来にむかってのみ(つまり65歳以降に納めたことになる)保険料納付済の効力を発生させるため受給権は発生しない
おっしゃっているこの部分ですが、これも60法附則18条に根拠があります。
同条に「同日以後の国民年金の被保険者期間を有するに至ったことにより」とあります。「同日」は条文の冒頭にあるとおり「65歳に達した日」です。
後納保険料の規定を定めた「国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成23年法律第93号)」により、後納保険料の制度により納付された保険料は、60法附則18条の「同日以後の国民年金の被保険者期間」を「同日以後に国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成23年法律第93号)附則第2条第1項の規定による納付が行われたことにより保険料納付済期間」に読み替えて60法附則18条を適用することになっています。
読み替えた6法附則18条は、「65歳に達した日において、保険料納付済期間(略)又は保険料免除期間(略)を有する者であって次の各号のいずれにも該当しなかったものが、同日以後に国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成23年法律第93号)附則第2条第1項の規定による納付が行われたことにより保険料納付済期間を有するに至ったことにより次の各号のいずれかに該当することとなったときは、同法第26条に定める老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢基礎年金を支給する。」となります。
読んでお分かりの通り、「同日(65歳に達した日)以後に・・・保険料納付済期間を有するに至った」ことにしか扱われないため、後納保険料による保険料納付済期間しか無いのであれば、「65歳に達した日において、保険料納付済期間(略)又は保険料免除期間(略)を有する者であって」を前提とする60法附則18条の適用はありません。
こうやって見ていくと、質問された方の疑問となった部分は、後納保険料の制度の特徴というより、法26条とそれをカバーするべき60法附則18条の特徴により生じる疑問ではないかと思います。
poo_zzzzz 2025-05-08 09:29:27