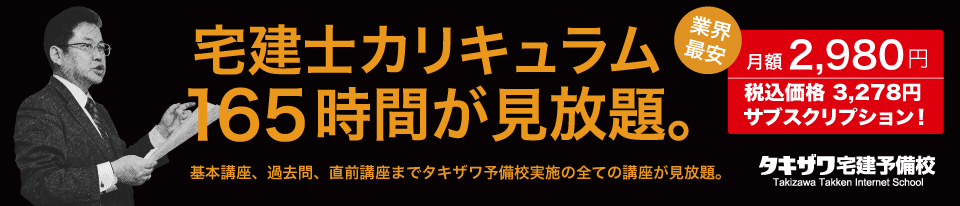ニックネーム | *** 未ログイン ***
権利関係 [過去問]/肢別過去問>権利関係>p120>問3
achiwa.76 2018-06-28 18:50:33
瀧澤先生
こんにちは。
肢別過去問>権利関係>p120>問3 に関しまして、
「Aは、Cに対し、Bに対する賃料(賃借料)の限度で、支払いを請求できる。」
で、回答は○で正解となっておりますが、
自分の理解では、
「Aは、Cに対し、Bに対する賃料(賃借料)とCに対する賃料(転借料)の
いずれか少ない限度で、支払いを請求できる。」
が正しく、回答は×が正解と思うのですが、どう理解したらよろしいでしょうか?
恐れ入りますが、ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。
achiwa.76さん、こんにちは。
まず、
〉「Aは、Cに対し、Bに対する賃料(賃借料)とCに対する賃料(転借料)の
〉いずれか少ない限度で、支払いを請求できる。」
という理解は正しいです。その点は、解説にも記載されていますよね?
あとは、本問を日本語的にどう理解するかの問題です。
本問は、「(賃貸人)Aは…(転借人)Cに対し、『Bに対する賃料』を…支払うよう請求することができる」か、という問い方になっています。
つまり、賃貸人が転借人に転借料と同額の支払いを請求できるかどうかが問われています。
この点、賃貸人は賃貸料>転借料であれば転借料と同額を転借人に請求できます。
ただし、賃貸料<転借料であれば、賃貸料が上限となります。
そして、本問も「賃貸人は原則として転借料と同額を転借人に請求できるが、賃貸料<転借料であれば例外的に賃貸料が限度となる」との意味だと読み取れます。
したがって、○と判断します。
「Bに対する賃料」=転借料と同額の支払いを請求できるかどうか、という問い方になっているところが読み取りのポイントですね。
賃貸料>転借料の場合に、賃貸料と同額を請求できると読み取る余地がなくなるからです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:0人
nobori_ryu 2018-06-28 08:34:44