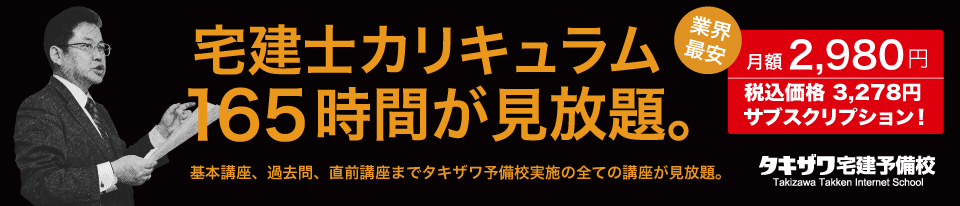ニックネーム | *** 未ログイン ***
権利関係 [過去問]/賃貸人の転借人への賃料請求について
bmw1025 2018-07-12 06:34:51
肢別過去問集
権利関係P121問3の解答ついて
この問題を解くにあたり、
「転借料が賃借料より少ない場合は、賃貸人は転借料を限度にしか請求できないのではないか」
と考えていたため、回答を誤ってしまいました。
回答文をよく読んでみますと、要するに、「転借料が賃借料より多いか、少ないかに関係なく、
賃貸人は、転借人に対して賃借料を限度として請求できるが、
転借人は、賃貸人の請求に対して請求額を限度に転借料(自分の負っている債務)を支払えば足りる」
というように理解すればよいのかな、と思っていますが、
このような理解で間違いないでしょうか。
bmw1025さん、こんにちは。
その解釈は、正しいとは言えません。
この問題は、問題文を日本語としてどう読み取るかに尽きます。
同じ問題について、1週間ほど前に同趣旨の質問があったので、こちらをご覧ください。
http://smon-hiroba.net/tk/bbs_each.php?rcdId=1818
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:0人
nobori_ryu 2018-07-06 00:32:16
ご回答ありがとうございました。
achiwa76様が既にご質問されていることに気付かず
同様の質問をしてしまいましたことを大変申し訳なく思っています。
先生のご回答にあるとおり「問題文の日本語をどう読み取るかに尽きる。」
とのことでしたので、再度、問題文をよく読み、achiwa76様への回答も読んでみました。
つまり、「Aは、Bに対する賃料(①)の限度で、Cに対し、Bに対する賃料(②)を自分に直接支払うよう請求することができる。」
との問題文の中に、「Bに対する賃料」という表現が2箇所使われていますが、
①の「Bに対する賃料」は賃料のことで、②の「Bに対する賃料」は転借料のことだということですね。
先生ご指摘のとおり、この問題は確かに日本語の読解力の問題なのかもしれませんが、
②の表現を「CのBに対する賃料」、あるいは「Bに対する転借料」とすれば、
受験生にとって理解しやすい問題文になったのではないかと思いますが、如何でしょうか。
bmw1025 2018-07-06 16:29:26
〉②の表現を「CのBに対する賃料」、あるいは「Bに対する転借料」とすれば、
〉受験生にとって理解しやすい問題文になったのではないかと思いますが、如何でしょうか。
うーん、どうなんでしょう?
この問題は、よく質問が出るのですが、②を「Bに対する転借料」と正しく理解したうえで、×ではないかと質問される方が大半であるように思います。
つまり、achiwa.76さんのように、賃貸料>転借料の場合に、「Bに対する賃料(=賃貸料)の限度で」支払いを請求できるわけではないから×なのでは?という疑問を持つ方の方が多いように思います。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:0人
nobori_ryu 2018-07-06 18:01:59
ご丁寧な回答ありがとうございました。
私が回答を間違えましたのは、②の「Bに対する賃料」を賃料と理解したところにそもそもの原因があるのですが、
設問を私が誤解したような設問に変えた場合の回答は、どのようになるのでしょうか。
つまり、AがCに対し賃料の限度で、賃料を請求したとすると、
転借料が賃料よりも多いときは、Cに賃料を請求できますが、
転借料が賃料よりも少ないときも、Cに賃料を限度に請求はできますが、Cは転借料を支払えば足りることになるので、
答えは○ということになるのでしょうか。
Aは、そもそも転貸を承諾したからといって、転借料を知っているとは限らないし、
AはBに対する賃料を確保するためにCに賃料を請求するのだから、
一般的にはAはCに転借料を請求するのではなく、テキストP189にもあるとおり、賃料を請求するのではないでしょうか。
一方、Cは転借料を支払うという債務を負っているに過ぎないので、
Aから賃料の請求があったとしても、転借料より多い額の請求には転借料を、転借料より少ない額の請求には請求額(賃料)を
支払えば足りる、と考えますと、②を賃料と誤解したとしても、○という解答が導き出せるのではないでしょうか。
bmw1025 2018-07-10 22:27:57
〉転借料が賃料よりも少ないときも、Cに賃料を限度に請求はできますが、Cは転借料を支払えば足りることになるので、
〉答えは○ということになるのでしょうか。
違います。
Cは転借料を支払えば足りるのですから、結局、Aは転借料を限度としてしかCに支払いを請求することはできないと理解すべきです。
説明の仕方を変えると、この場合、Aがいくらまで転借人に請求できるかではなく、いくらまで転借人から受領できるか、という意味で理解すべきです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:0人
nobori_ryu 2018-07-11 01:56:07
早速のご回答有難うございます。
テキストP189には、「賃貸人は転借人に賃料を請求できる。もっとも、転借人は、賃借料と転借料の、
いずれか少ない額を支払えば足りる。」と説明されています。
また、補足説明の箇所にも「民法はバランスをとるために、転借人にも賃料を請求できるとした。」
と説明されています。
以上のことから、「転借料が賃料よりも少ないときも、Cに賃料を限度に請求できますが、Cは転借料を支払えば足りることになるので、
答えは○」という回答を考えたのですが、やはり誤りなのでしょうか。
先生からは、「…と理解すべきです。」との回答をいただいていますが、
私のように考える余地もあるということでしょうか。
bmw1025 2018-07-11 04:11:20
〉「転借料が賃料よりも少ないときも、Cに賃料を限度に請求できますが、Cは転借料を支払えば足りることになるので、
〉答えは○」という回答を考えたのですが、やはり誤りなのでしょうか。
誤りです。「Cに賃料を限度に請求できますが」の部分が誤りです。
テキストP189欄外に記載の通り、賃借料が10 万円、転借料が8万円の場合、転借人は8万円を支払えば足りるのに、
bmw1025参のお考えだと、「賃貸人は10万円を請求できる」を○とすることになります。それはおかしいでしょう?
それで納得できなければ、次のような場合はいかがですか?
AはBの運転する車にはねられ、入院治療費等300万円相当の損害を受けたので、300万円の賠償を求める訴訟を提起しました。
しかし、Aにも急に車道に飛び出したという過失があり、裁判所は過失相殺の結果、Bに150万円の賠償を命ずる判決を出しました。
この場合、Aが300万円の賠償を求めて訴訟を提起することは違法ではありません。しかし、これを「AはBに対して300万円の賠償を請求できる」と記載してあれば、×と判断するはずです。それと同じことですよ。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:0人
nobori_ryu 2018-07-11 23:38:23
私にも分かるように説明していただき誠に有難うございました。
今回のことを機にいろいろ調べていましたら、
現在の民法613条1項が「賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、
賃貸人と転貸人との間の賃貸借に基づく債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。」
というように改正されていることを知りました。
設問が、改正後の条文のように書かれていれば、日本語の問題も発生しなかったように思いました。(負け犬の遠吠え?)
しつこい質問にお付き合いいただきまして、本当に有難うございました。
bmw1025 2018-07-12 06:34:51