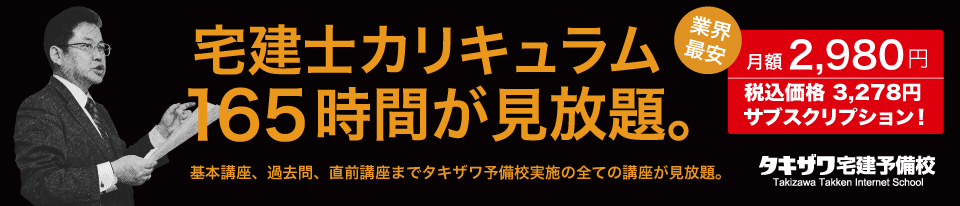ニックネーム | *** 未ログイン ***
権利関係 [過去問]/借地借家法(借家)
buutake 2020-05-24 09:24:03
瀧澤先生 こんばんは
肢別過去問(権利関係)P134 問17(19-12④)
AがBに対し、A所有の甲建物を3年間賃貸する旨の契約をした。Bが適法に甲建物をCに
転借していた場合、AはBとの賃貸借契約が解約の申入れによって終了するときは、
特段の事情がない限り、Cにその胸を通知しなければ、賃貸借契約の終了をCに対抗する
ことができない。
答え ○
賃貸借契約が、解約申入れによって終了する場合、賃貸人は転借人に賃貸借契約が終了
することを通知しなければ、賃貸借の終了を転借人に対抗できない。
質問事項
転借人がいる場合の 解約申入れ が、
基本テキストP.203 に記載の民法の合意解約と、P.217に記載の借地借家法の
解約申入れが混同してしまい、違いがよく理解できません。
で、本19-12④も
賃貸人の解約申入れは民法の合意解約同様に
賃貸人と賃借人が、グルになって合意解約を悪用している可能性があり、
転借人に終了を通知するだけでは、終了を転借人に対抗できないのでは?
と思いました。
申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
ぶ〜たけ
ぶ~たけさん、こんにちは。
まず、基本テキストP203の「原則」にある通り、賃貸借が終了すると賃貸人はそれを転借人に対抗でき、転借人に目的物の明渡しを求めることができます。
言い換えると、賃貸借の終了により、賃貸人は目的物を取り戻すことができるのが原則だということです。
転貸を承諾しているとはいえ、賃貸借が終了した以上、賃貸人に目的物の取戻しを認めるのは当然です。
そして、賃貸借が期間の定めのないものである場合、賃貸人が賃貸借契約を終了させる方法は、「解約の申し入れ」です(なお、この問題は、「A所有の甲建物を3年間賃貸する旨の契約をした」とありますが、その後に「Bとの賃貸借契約が解約の申入れによって終了するときは」とあるので、既に契約が更新されて、現在は期間の定めのない賃貸借となっているとご理解ください。そういう意味では、ちょっと不親切な問題ですね。)。
したがって、「解約の申し入れ」は賃貸人にとっては当然の権利行使であり、賃貸借は終わるべくして終わったものと考えることができます。
よって、原則通り、賃貸人に目的物の取戻しを認めるべきなのです。
ただし、賃貸借の終了に伴って、転借人が建物から突然追い出されることになるのは気の毒です。
そこで借地借家法は、建物の賃貸借の場合は転借人への通知を必要とし、かつ、通知後6カ月経過しないと転借人を追い出すことはできないと規定しているのです。
一方、合意解除は、たとえば3年間の期間を定めて賃貸借契約を結んだが、賃貸人が途中で契約を打ち切りたいと考えた場合に、賃借人との合意で契約を終了させるものです。
3年間と約束したわけですから、本来、賃貸人が途中で契約を一方的に打ち切ることはできません。
しかし、賃借人との合意が成立すれば、途中で契約を打ち切ることができるのが合意解除です。
そういう意味で、合意解除は「解約の申し入れ」とは異なり、本来は終了するはずのなかった賃貸借が終了しているわけです。
転借人の立場に立てば、少なくとも賃貸借契約が存続する間は転借物を使用できるはずだったのが、終了するはずのないタイミングで突然、賃貸借が終了し、転借物を賃貸人に返還せざるを得ない状況に追い込まれるわけです。
つまり、身勝手な賃貸人よりも転借人を保護する必要性が高いのです。
なので、合意解除で賃貸借が終了しても、転借人を追い出すことは認めないのです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:0人
nobori_ryu 2020-05-24 08:16:21