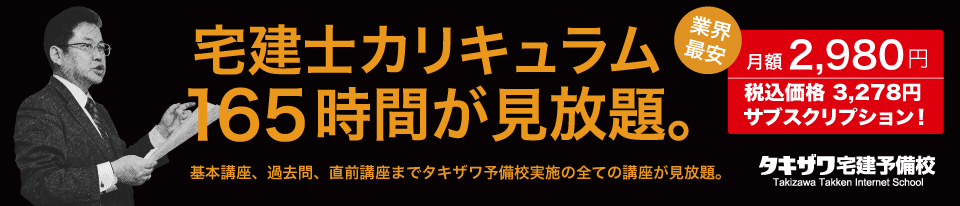ニックネーム | *** 未ログイン ***
権利関係/無効と取消しの区別
tommy67 2017-06-12 12:29:47
滝沢先生
お忙しい中、失礼致します。
民法の意思表示や制限行為能力制限などで、無効になる場合と取消しになる場合の区別がいまいち出来ず、この場合はどっちだっけ?という具合でつまずいています。何か良い法則などがありましたら、教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願い致します。
tommy67さん、こんにちは。
AB間の売買契約における売主Aを例にすると、Aに「売りたい」という気持ち(内心的効果意思と呼びます)があるかないかです。
虚偽表示、心裡留保、錯誤により「売ります」という意思表示を行ったAには、「売りたい」という内心的効果意思がありません。したがって、いずれも意思表示は無効となります(ただし、心裡留保は相手方保護のため、原則として有効となり、一定の要件を充足する場合のみ無効)。
一方、詐欺、強迫により「売ります」という意思表示を行ったAには、騙されたにせよ、脅されたにせよ、「売りたい」という内心的効果意思が認められます。したがって、意思表示は有効ですが、「売りたい」という気持ちの形成過程に瑕疵があるので、取消しが認められるのです。
また、意思能力がない者は、有効な内心的効果意思を形成する能力がないため、意思表示は無効となります。
ちなみに、いったん契約したら守らなければならないという民法の大原則も、内心的効果意思から説明がつきます。
すなわち、AとBは誰からも強制されることなく、自由な立場で自ら「売りたい」「買いたい」という内心的効果意思を形成して契約を締結したのだから、その契約に拘束されることになる。
以上、意思表示に関する基礎理論を極めて簡潔にまとめました。
この説明で理解が難しければ、諦めて暗記してください(笑)
なお、先日成立した改正民法では、錯誤は「無効」から「取消し」に変わります。この点を、どう理論的に説明するのかは不明です。
瀧澤
参考になった:2人
nobori_ryu 2017-06-12 11:35:30
ご回答ありがとうございました。
とてもとてもスッキリしました。
内心的効果意思が認められるか否かで、取消しか無効かになるのですね。
ご教授ありがとうございました。
tommy67 2017-06-12 12:29:47